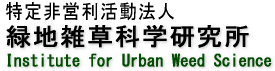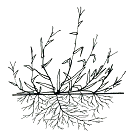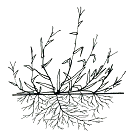|
|
| 2025.01.05 |
当法人の会誌「草と緑」16巻(2024年)が、J-STAGEに掲載されました。
掲載記事はこちらからご覧ください
☆J-STAGE「草と緑」トップページ⇒ |
| 2024.11.22 |
令和6年度緑地雑草科学講演会が11月11日(月)に開催されました。
・テーマ「雑草に関する法規制-植物防疫法改正をきっかけに-」
・講師:黒川俊二氏
☆オンラインで、68名の参加がありました。関連記事はニュースレター16号に掲載の予定です。 |
| 2024.10.15 |
令和6年度緑地雑草科学講演会が開催されます。
・テーマ:雑草に関する法規制-植物防疫法改正をきっかけに-
・11月11日(月)13時30分~15時30分 Zoomによるオンライン開催
・講師:黒川俊二氏(京都大学)
・申込:メール申込 (k-saji(at)bousou-ken.org まで)
※ (at) は@に置き換えて下さい.
・申込期限: 11 月 6 日(水)
☆講演会のご案内はこちらから⇒ |
| 2024.04.01 |
令和6年度総会が3月29日、特定非営利活動法人緑地雑草科学研究所事務所にて開催され、全議案が可決承認されました。
総会資料はコチラから⇒ |
| 2024.01.30 |
当法人企画の「ゴルフの好きな人も そうでない人も知ってほしい-列島ゴルフ場の科学」が販売中です。
☆列島ゴルフ場の科学⇒ |
| 2024.01.05 |
当法人の会誌「草と緑」15巻(2023年)が、J-STAGEに掲載されました。
掲載記事はこちらからご覧ください
☆J-STAGE「草と緑」トップページ⇒ |
| 2023.12.01 |
令和5年度定例講演会が11月14日(火)に開催されました。
・テーマ「地域の緑地生態系を支える日本列島のゴルフ場」
・講師:伊藤幹二氏 伊藤操子氏
☆オンラインで、59名の参加がありました。 |
| 2023.10.17 |
令和5年度緑地雑草科学講演会が開催されます。
・テーマ:地域の緑地生態系を支える日本列島のゴルフ場
・11月14日(火)Zoomによるオンライン開催
・講師:伊藤幹二氏・伊藤操子氏(マイクロフォレストリサーチ株式会社)。
☆講演会のご案内はこちらから⇒ |
| 2023.04.02 |
令和5年度総会が3月29日、特定非営利活動法人緑地雑草科学研究所事務所にて開催され、全議案が可決承認されました。
総会資料はコチラから⇒ |
| 2023.01.05 |
当法人の会誌「草と緑」14巻(2022年)が、J-STAGE(科学技術振興機構が運営する電子ジャーナルプラットフォーム)に掲載されました。
詳しくはこちらをご覧ください⇒ |
| 2022.11.05 |
令和4年雑草インストラクター養成講座を実施しました。 |
| 2022.11.01 |
草刈り・除草ワールド 2022で当NPOの雑草インストラクター3名がセミナーを行いました。
|
| 2022.08.30 |
令和4年度緑地雑草科学講演会が、7月4日(月)にオンラインで開催されました。
・テーマ:「‘草’は表土を創り育む:私たちが忘れた大事なこと」
・講師:伊藤幹二氏。
☆73名の参加がありました。関連記事は「草と緑」第14巻に掲載される予定です。 |
| 2022.06.13 |
令和4年雑草インストラクター養成講座を9月から実施します。
養成講座開催は、本年度の募集を以って、一時終了予定しています。雑草管理に必須な基礎知識や実践的な応用力の習得を希望する方は、ぜひこの機会に受講ください。
☆2022年度雑草インストラクター養成講座募集要項⇒
☆インストラクター養成講座の趣旨⇒
|
| 2022.06.12 |
令和4年度緑地雑草科学講演会が開催されます。
・テーマ:‘草’は表土を創り育む:私たちが忘れた大事なこと
・7月4日(月)Zoomによるオンライン開催
・講師:伊藤幹二氏(マイクロフォレストリサーチ株式会社)
☆講演会の案内はこちらから⇒ |
| 2022.04.08 |
令和4年度総会が3月29日、特定非営利活動法人緑地雑草科学研究所事務所にて開催され、全議案が可決承認されました。
総会資料はコチラから⇒ |
| 2022.03.03 |
令和3年度雑草インストラクター養成事業により、このたび新たに8名が認定され、「雑草インストラクター」は総勢42名となりました。
|
| 2022.01.08 |
当法人の会誌「草と緑」13巻(2021年)が、J-STAGE(科学技術振興機構が運営する電子ジャーナルプラットフォーム)に掲載されました。
詳しくはこちらをご覧ください⇒ |
| 2021.11.27 |
当法人は、2021草刈り・除草ワールドで行われたセミナーのテーマ・講師の選定を担当させていただき、セミナー出講およびブース出展をいたしました。
|
| 2021.07.19 |
令和3年度の定例講演会が7月19 日に オンラインで 開催されました。
テーマ「農薬の 安全性について」 講師:與語靖洋 氏
73 名の参加がありました 講演。内容は草と緑第13巻に公表されています。
J-STAGEの公開資料⇒ |
| 2021.03.26 |
令和3年度総会が3月26日、特定非営利活動法人緑地雑草科学研究所事務所にて開催されました。
総会資料はコチラから⇒ |
| 2021.01.31 |
「草と緑」第12巻(2020)の各記事が,J-STAGE(科学技術振興機構)の記事検索サイトに公開されました。https://www.jstage.jst.go.jp/browse/iuws/-char/ja |
| 2020.11.13 |
当法人は、2020草刈り・除草ワールドで行われたセミナーのテーマ・講師の選定を担当させていただき、セミナー出講およびブース出展をいたしました。 |
| 2020.06.01 |
「草と緑」第11巻(2019)の各記事が,J-STAGE(科学技術振興機構)の記事検索サイトに公開されました。 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/ |
| 2020.04.01 |
令和2年度総会が3月26日、特定非営利活動法人緑地雑草科学研究所事務所にて開催されました。
総会資料はコチラから⇒ |
| 2020.04.01 |
「草と緑」第11巻を刊行しました。 |
| 2020.02.13 |
令和元年度雑草インストラクター養成事業に基づき、この度新たな「雑草インストラクター」6名が認定されました。これにより現在、合計34名の「雑草インストラクター」登録となりました。 |
| 2019.12.01 |
当法人は、2019草刈り・除草ワールドで行われたセミナーのテーマ・講師の選定を担当させていただき、セミナー出講およびブース出展をいたしました。 |
| 2019.05.01 |
平成31年度の定例講演会が3月29日、名古屋VIP貸会議室名古屋駅前店にて開催されました。
テーマ:「砂漠化対処のための土地・植生の診断・治療・予防ーモンゴル・中国を事例にー」 |
| 2019.04.10 |
平成31年度総会が3月29日、名古屋VIP貸し会議室名古屋駅前店にて開催されました。
総会資料はコチラから⇒ |
| 2019.04.06 |
2018年の雑草インストラクター養成事業に基づき、この度新たな「雑草インストラクター」10名が認定されました。これにより現在、合計28名の「雑草インストラクター」が登録されています。 |
| 2019.02.07 |
定期刊行物「草と緑」第10巻(2018)の記事が,J-STAGE(科学技術振興機構)の記事検索サイトに公開されました。
|
| 2018.09.21 |
日経BP社の「日経クロステック」および「メガソーラービジネス」に、第8回目となる当研究所のインタビュー記事が掲載されました。
グリーンモンスター「クズ」に立ち向かうには? 緑地雑草科学研究所に聞く
(第8回・特別編)。
☆第8回特別編の掲載記事はコチラをご覧ください⇒
★過去の掲載記事は下記からご覧ください。
第1回:「10の雑草リスクに備えよ」
第2回:「5つの雑草対策を組み合わせる」
第3回:「間違った雑草対策でメガソーラが悪者に」
第4回:「雑草の繁殖戦略に除草剤で対抗する」
第5回:「被覆植物(地被植物、カバープランツ)」  前半⇒ 前半⇒  後半⇒ 後半⇒
第6回:「マルチ(土壌被覆資材)について」  前半⇒ 前半⇒  後半⇒ 後半⇒
第7回:「刈り取り」  前半⇒ 前半⇒  後半⇒ 後半⇒
|
| 2018.09.07 |
公開シンポジウム「雑草・人・環境シリーズ」ご案内!!
テーマ:クズ問題とどう取り組むか-その科学と技術-
■日時:2018年10月14日(日)
☆詳しくはコチラをご覧ください⇒
|
| 2018.09.07 |
新出版物のご案内!!
「葛とクズ-古来の有用植物がいま強害雑草に」
☆詳しくはコチラをご覧ください⇒
|
| 2018.04.09 |
平成30年度総会が3月29日、名古屋VIP貸し会議室名古屋駅前店にて開催されました。
総会資料はコチラから⇒ |
| 2018.04.09 |
平成30年度の定例講演会が3月29日、名古屋VIP貸し会議室名古屋駅前店にて開催されました。
テーマ:「雑草を見分け、調べる」 |
| 2018.01.26 |
「草と緑」第9巻を刊行しました。 |
| 2017.10.30 |
第8回目公開シンポジウム、「雑草・人・環境シリーズ」
葛からクズへ-日本古来の有用植物がいま強害雑草に-が開催されました。
公開シンポジウムの内容⇒ |
| 2017.07.01 |
定期刊行物「草と緑」の第1巻(2009)~第8巻(2016)の記事が,J-STAGE(科学技術振興機構)の記事検索サイトに公開されました。
J-STAGE掲載「草と緑」⇒ |
| 2017.04.04 |
平成29年度総会が3月28日、兵庫県民会館にて開催されました。
総会資料はコチラから⇒ |
| 2017.04.04 |
平成29年度の定例講演会が3月28日、兵庫県民会館にて開催されました。
芝生の世界-その基礎から利用まで- |
| 2017.03.08 |
講演会「芝生の世界-その基礎から利用まで-」の開催が決定しました。 |
| 2017.01.20 |
2016年度より開始された雑草インストラクター養成事業に基づき、「雑草インストラクター」を認定しました。 |
| 2017.01.11 |
「草と緑」第8巻を刊行しました。 |
|
|